|
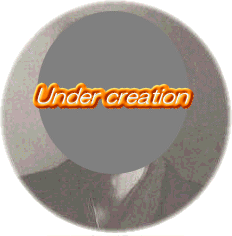 成瀬重吉は、1859年(安政6年)10月29日、梁田郡島田町の豆腐屋の政五郎の子として生まれました。9歳で荒金村の北辰堂に入門しました。その後、覚本寺の住職(お寺の主のお坊さん)の植野秀明という人に習い、次に、八幡小教院で国学という学問を学びました。そして、川上広樹という人の弟子になりました。重吉の学問好きは有名で、少年のころ、父が冬の着物を買うようにとくれたお金で自分の好きな本を買ってしまったという話が残っているほどです。 成瀬重吉は、1859年(安政6年)10月29日、梁田郡島田町の豆腐屋の政五郎の子として生まれました。9歳で荒金村の北辰堂に入門しました。その後、覚本寺の住職(お寺の主のお坊さん)の植野秀明という人に習い、次に、八幡小教院で国学という学問を学びました。そして、川上広樹という人の弟子になりました。重吉の学問好きは有名で、少年のころ、父が冬の着物を買うようにとくれたお金で自分の好きな本を買ってしまったという話が残っているほどです。
重吉は、20歳から自分のふるさとの小学校にしばらくつとめていましたが、40歳で試験を受けて、国漢(国語と中国の文の勉強)、修身(今の道徳)、法制経済(国の決まりと物やお金の流れ)を中等学校で教えることができる免許状をとりました。中等学校では宇都宮の下野中学校をはじめに、佐野中学、足利工業、栃木中学の各校につとめました。地元の足利工業には1912年(明治45年)4月から1915年(大正4年)3月までつとめ、寄宿舎(家をはなれて通学する生徒が生活するところ)の舎監(生徒のめんどうをみる役)をしました。こうして、42年間学校教育の仕事をしていた重吉は、1920年(大正9年)、62歳でふるさとへ帰りました。
ふるさとに帰った重吉は、農業研究会をつくるなど、農業の仕事をがんばっていました。その中で注目すべきことは、堆肥(わら・草などをつみかさねて、くさらせたひりょう)を使って作物を作ることをすすめたことです。後に農業指導の立派な様子が認められ、1933年(昭和8年)に表彰を受けています。
そして重吉の一生で、最も注目すべきことは、ふるさとの若い人たちの指導のために夜学校をつくったことです。その名前は「泗南夜学校」といいます。泗南とは渡良瀬川の南という意味です。重吉は、1922年(大正11年)9月9日、私立泗南夜学校をつくる許可を栃木県にお願いし、同年11月30日に認められました。この夜学校の入学資格は青年学校卒業以上の男子でした。定員は10人、卒業までの期間は3年、授業の時間は午後7時から10時まで1週18時間、教科は修身、国語、漢文、法制経済でした。しかも「本校一切ノ費用ハ設立者ノ負担トス」とあり、授業料は全くとらず、すべて重吉とその家族のお金で間に合わせていました。退職金を使って自宅を新築した重吉は、その12畳の座敷を勉強する場所として使いました。校長と先生が重吉、書記が成瀬精一でした。このたった2人が泗南夜学校の全部の職員でした。生徒は地元の御厨町だけでなく、梁田、筑波、それに足利市、群馬県の山田郡矢場川村、同郡休泊村、邑楽郡中野村などから通学しました。1941年(昭和16年)に閉鎖、廃校になるまでに全部で137名の卒業生を出しています。
1933年(昭和8年)には栃木県知事、1940年(昭和15年)には文部大臣からそれぞれ教育功労者として表彰を受けています。自分のお金を出して、夜学校をつくり、ふるさとの青年たちを育てたことが世に認められたわけです。重吉は、1942年(昭和17年)10月1日、84歳で亡くなりました。
|